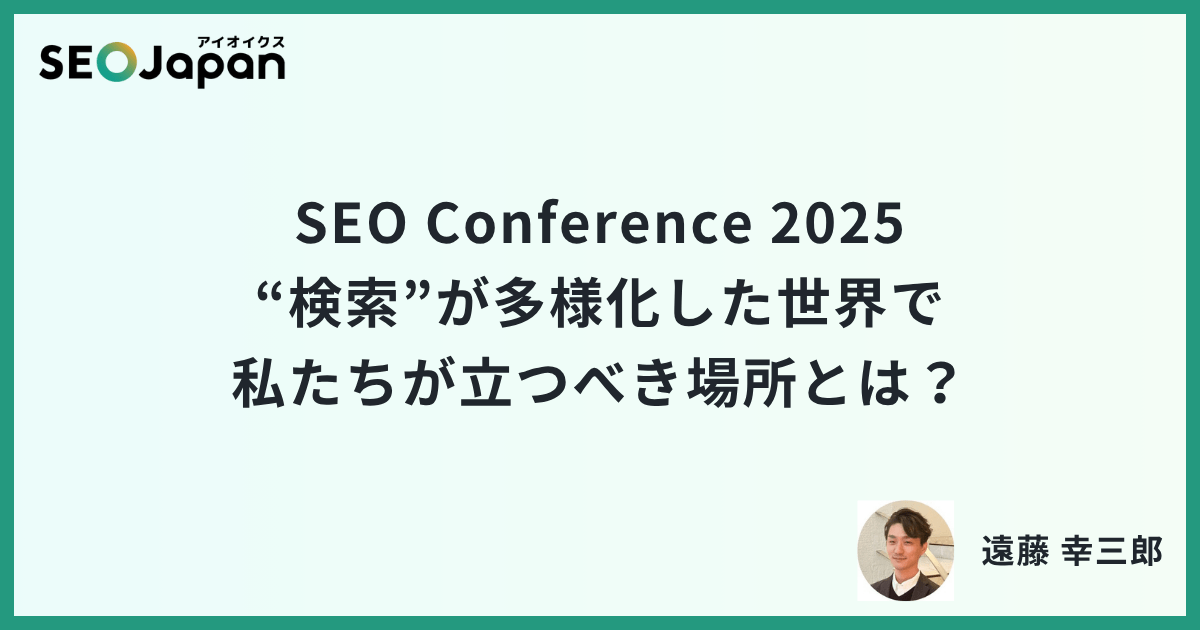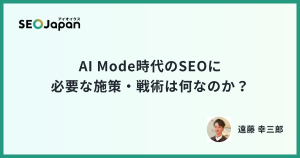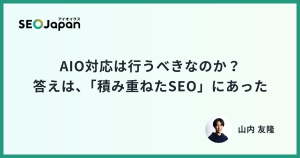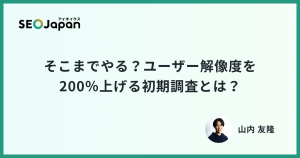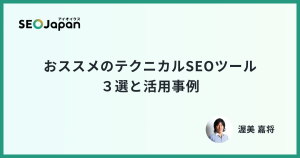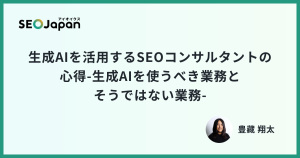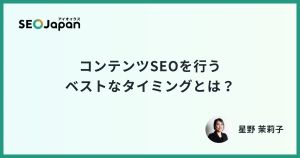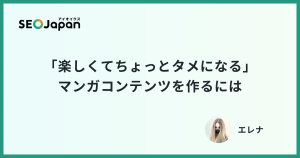2025年7月17日にリアルとオンラインのハイブリットで開催されたJapan SEO Conferenceに参加してきました。
リアルの会場は応募者が殺到し、抽選となったなか当選するかドキドキしていましたが、日ごろの行いが良かったため(?)に無事当選しまして、東京駅近くのカンファレンス会場での参加が叶いました。
主催はミエルカを提供するFaber Companyさん(@Mieruca_kun)。日本でSEOの冠がついたこれまでで最大規模の本カンファレンスですが、特に「AIによる検索の変化」と「SEOの再定義」に触れられるセッションが多く、示唆に富む内容でした。
印象に残ったトピック3つ
セッションでも随所で語られていたのが「生成AIの台頭でSEOの役割は終わるのか?」という問い。
もちろん答えはNoですが、「では何をすべきか?」についての示唆がいくつもありました。
1. 生成AI時代の“良質なコンテンツ”とは?
もっとも印象に残ったセッションは、「生成AI活用でSEOにも強い『良質なコンテンツ』を作る方法」。
登壇者はカインズの与那覇さん(@kazufumi478)、WEBライダーの松尾さん(@seokyoto)、ナイルの森さん。
コンテンツの作成方法にAIをどの程度使うか?に焦点が当たったセッションでしたが、与那覇さんが語った「AIに大根は育てられない」という言葉が強く記憶に残っています。
AIによって情報の要約や整理の工数は大きく削減できるようになりましたが、実際に現場で体験し、具体を拾う力は人間にしかできないという主張には大きくうなずきました。
AIによる情報の大量生産が当たり前になる時代だからこそ、一次情報の価値は相対的に高まっていると感じます。実際、弊社のクライアントワークでも、生成AIで作成した記事草案をもとに、現場担当者からヒアリングしてエピソードや実例を肉付けするプロセスが増えています。
“AIが素材をつくり、人間が価値を注入する”という役割分担が、今後の良質なコンテンツ制作の基本形になると感じています。
2. コンテンツに必要な“深さ”とは?
最終セッション「AI時代のSEOはどうなるのか?」では、渡辺さん(@takahwata)が「AIによってクエリファンアウトのような技術が進化し、より深い情報が求められている」と述べていた点も印象的でした。
(あのイベントのあとに、渡辺さんが二次会で聞かれた内容をハイスピードでブログ更新していて驚愕でした。情報の掴み方、選定方法として参考になりました。こちらもぜひ → 私が信頼する情報源と独自の選別術 – SEMリサーチ)
これは私自身も実務で感じている部分で、従来の予定調和的なコンテンツではなく、検索意図の奥行きに応えるような“深さ”のあるコンテンツ設計が、より重要になるという共通認識を持てました。
よくあるWebだけで集めた一般的な情報のまとめ(こたつ記事)よりも、購入した実体験をまとめた内容や、事例のストーリーをまとめたコンテンツ作成に注力するべき、と考えて良いと思います。
たとえば、とある決済系BtoB商材の競合性の高いテーマでは、単なる比較記事では戦えず、ユーザーのビジネスステージ別の意思決定フローや、経理部門の説得資料を含んだ意思決定支援型コンテンツが上位に食い込んできています。
これは“深さ=長さ”ではなく、“目的適合性の密度”であるという理解が必要だと感じています。
3. 他社の取り組みで感じた“当たり前の難しさ”
他社事例を聞いて、目新しい施策は正直あまりありませんでしたが、それはむしろ本質的で、「SEOに近道はない」ことの裏返しでもあると捉えています。
結局のところ、事業に即した“やるべきことをやる”の徹底が難しく、それゆえに価値がある。私たちのような支援会社が果たすべきは、その整理と実行案、そして部署を超えて実現するための丁寧な情報提供やコミュニケーションの支援だと改めて実感しました。
たとえば、あるクライアントでは“コンテンツ強化施策”の一環として内部リンクの再設計を進めていますが、実現にはSEO部門と広報、営業、さらには法務部門との調整が必要だったりします。
我々が不躾にいきなり直接のコミュニケーションをとることは難しいなかで、ご納得いただくためのデータや背景情報の整理などは、支援者が付加価値を出すべき領域かもしれません。
全体を通じて感じたこと
「答えは現場にある」ことを再認識
アイオイクスとしても、「生成AIで変わる検索」への対応をサービスメニューに反映し始めています。たとえば、FAQの再設計、一次情報を堀り起こすコンテンツ作成方法の強化、構造化マークアップの見直しなどです。
今回のカンファレンスを通じて、AIがあるからこそ「現場にしかないリアルな知見」が、ますます貴重になることを再確認しました。
AIによる生成コンテンツがあふれるいま、企業が語る「ストーリー」や「想い」に信頼の源泉が移っているように思います。
単に記事を量産するのではなく、“会社としてどう語るか”という構造化された発信が求められる。そうしたメッセージは、社内にも強く刺さる内容でした。
当社員ブログ含め、より情報の発信をしていくことはもちろん、その元となる日ごろのインプットとその情報のかみ砕き方、解釈の精度についても磨いていく必要があると感じています。
SEOの本質は「事業が主体」
多様化する検索チャネル(SNS・動画・生成AI)を前提としたマーケティングにおいて、SEOのスコープも広がっています。
単なる記事施策にとどまらず、事業者の“やりたいこと”を整理し、現実的な解に具体化し、実行に結びつける支援が必要だと改めて感じました。
多くのSEO施策は、「検索順位を上げる」「流入を増やす」という手段の達成に集中しがちです。
しかし、それが事業にとって意味のある指標でなければ、ただの“数値のための数値”に過ぎません。
SEOは、売上・問い合わせ・ブランド価値など、事業のKGIを支える構造の一部であるべきです。
たとえば、「検索流入を1.5倍にした」という成果があったとしても、それが
- CVに繋がっていない
- 自社の主力サービスと無関係なニーズを拾っている
- 営業やカスタマーサクセスの負荷だけを増やしている
のであれば、むしろ事業の足を引っ張る結果にもなり得ます。
「SEOをどうやるか」ではなく、「そもそも誰に何の情報を届けるべきか」が主であり、それは「事業のなか」にしかありません。
だからこそ、SEOの本質は「事業が主体」であると、当たり前ですが主従逆転してはいかんな、と思いました。
おわりに
検索が“Googleの箱の中”に収まらなくなってきます。
SEOは終わるのではなく、進化する局面にあるのだと、今回のイベントを通して強く感じました。
SEOの最前線で戦う皆さんの視点に刺激を受けながら、自社の立ち位置と進化の方向性を見つめ直す、非常に有意義な時間となりました。
Xにて#JSC25と検索すると、とても盛り上がっていた現場の熱気を感じることができます。
ノベルティシールに「GEO」があるのはタイムリー。

本田さん(@hontaku)はじめ、Faberの皆さま、熱のこもった場づくりをありがとうございました!
アイオイクスではSEOを軸としたWebコンサルティングサービスを提供しています。
いわゆるSEOの型に沿った施策ではなく、お客様の事業やWebサイトの構成を踏まえた最適な施策のご提案を重要視しています。SEOにお困りの際はぜひご相談ください。
→SEOコンサルティング サービスページ
アイオイクスでは一緒に働く仲間を募集しています
アイオイクスのWebコンサルティング事業部では、「一緒に挑戦し、成功の物語を共有する」という理想像を掲げ、本質的な取り組みを推進しています。私たちと汎用性の高いスキルを突き詰め、自由に仕事をしていきませんか。
メールマガジンの登録はこちら
SEOに関連する記事の更新やセミナー情報をお届けします。